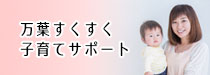本文
国民健康保険
国民健康保険とは
病気やけがに備えて被保険者のみなさんが保険料(税)を出し合い、医療費の給付を行う相互扶助の制度です。
加入や脱退する場合は届出が必要です
職場の健康保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除くすべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。退職して職場の健康保険をやめたとき、転入したとき(外国籍で職場の健康保険に加入せず、3か月を超せて日本に滞在するとき)は、国保への加入の手続きが必要になります。また、国保に加入している方が他の健康保険に加入したり、転出するときは、国保の脱退の手続きをしてください。これらの手続きは、原則14日以内に届出することと規定されています。
届出にはマイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類も一緒にお持ちください。
| 入るとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村から転入したとき | 他の市町村発行の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 |
| 職場の健康保険の被扶養者から外れたとき | 被扶養者になれない旨の証明書 |
| 子どもが生まれたとき | 保険証・母子手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
| 外国籍の方が加入するとき | 在留カード |
| やめるとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村へ転出するとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国保・職場の資格確認書または資格情報のお知らせ ※未交付の場合は、加入を証明するもの |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保・職場の資格確認書または資格情報のお知らせ ※未交付の場合は、加入を証明するもの |
| 国保の被保険者が死亡したとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書 |
| 外国籍の方がやめるとき | 在留カード、資格確認書または資格情報のお知らせ |
| その他 | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 村内で住所が変わったとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 世帯を分離したり、一緒にしたとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ |
| なくしたとき | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真付きのもので有効期限内の証明書 |
| 汚れて使えなくなったとき | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真付きのもので有効期限内の証明書 |
| 修学のため、別に住所を定めるとき | 在学証明書 |
マイナンバーによる情報連携
マイナンバーによる情報連携(情報照会)の開始に伴い、社会保険の資格喪失証明書等の各種添付書類が省略可能になりました。しかし、マイナンバーによる情報照会については、即日照会できない場合があります。即日交付を希望される場合は、引き続き各種添付書類の提出をお願いします。
国民健康保険税の算定方法と納め方
国保と保険税
国民健康保険に加入すると保険税を納めていただくことになります。国民健康保険税は次の合算額で納めることになります。
- 医療給付費分
皆さんが病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付費用として使われます。 - 後期高齢者支援金分
75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられます。 - 介護納付金分
介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用として充てられます。
保険税の決め方
- 医療給付費分の算定方法
次の(1)〜(3)の合計で各世帯の課税額が決定されます。
(1)所得割額:5.9%(所得に対して)
(2)均等割額:24,000円(1人について)
(3)平等割額:特定以外18,000円(1世帯について)特定世帯9,000円(1世帯について)
※賦課限度額:66万円(年税額が66万円を超える場合は、超える税額については課税しません。)
- 後期高齢者支援金分の算定方法
次の(1)〜(3)の合計で各世帯の課税額が決定されます。
(1)所得割額:2.0%(所得に対して)
(2)均等割額:8,400円(1人について)
(3)平等割額:特定以外6,000円(1世帯について)特定世帯3,000円(1世帯について)
※賦課限度額:26万円(年税額が26万円を超える場合は、超える税額については課税しません。)
- 介護納付金分の算定方法
次の(1)〜(3)の合計で各世帯の課税額が決定されます。
(1)所得割額:1.9%(所得に対して)
(2)均等割額:11,000円(1人について)
(3)平等割額:5,000円(1世帯について)
※賦課限度額:17万円(年税額が17万円を超える場合は、超える税額については課税しません。
※国保税の減額:所得が一定金額以下の世帯については均等割額及び平等割額をそれぞれ7割・5割・2割を減額する措置があります。
納税義務者
たとえ、世帯主が国保に加入していなくても納税義務者は世帯主です。(これを擬制世帯主といいます。)
国民健康保険税の納付月
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
国保の保険給付
病気やケガで医療機関にかかる際、義務教育就学前は2割、義務教育就学後から70歳未満は3割、70歳以上75歳未満の医療費は「国民健康保険資格確認書兼高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示することで2割<2014年4月1日までに満70歳(昭和19年4月1日以前生まれの方)になった者は、特例措置により1割>。(現役並み所得者は3割)の自己負担で診療が受けられます。ただし、次の場合は国保の給付は受けられません
- 普通分娩、健康診断、予防注射、美容整形など病気でない場合
- ケンカによるケガ、自己の故意の犯罪行為などで起きたケガ
- 仕事上の病気やケガで、労働基準法、労災保険法の適用を受ける場合
入院時の食事療養費の支給
入院時の食事代は、1食につき下表の金額を支払うだけで残りは国保から支払われます。
| 一般加入者 | 1食につき510円 |
|---|---|
| 住民税非課税世帯等の人(低所得2の人) 90日までの入院 |
1食につき240円 |
| 住民税非課税世帯等の人(低所得2の人) 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) |
1食につき190円 |
| 低所得1の人 | 1食につき110円 |
住民税非課税世帯等の人は
「標準負担額減額認定証」(低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となります。担当窓口で申請してください。また、入院期間が90日を越える場合は「領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをもって、再度担当窓口で申請してください。(マイナ保険証を利用する場合は不要です)
高額療養費支給制度
70歳未満の人
所得に応じて医療費を負担します。
医療費の負担が下表の限度額を超えたとき、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。
| 所得 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|---|
| 901万円を超える | ア | 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
| 600万円を超え 901万円以下 |
イ | 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算。 |
93,000円 |
| 210万円を超え 600万円以下 |
ウ | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算。 |
44,400円 |
| 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税 非課税世帯 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の人
| 課税所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%【140,100円】 | |
| 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%【93,000円】 | ||
| 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%【444,000円】 | ||
| 一般(課税所得145万円未満) | 18,000円 ※年限上限144,000円 | 57,600円【44,400円】 | |
| 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得1(所得が一定以下) | 8,000円 | 15,000円 | |
| 【】内は、過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の限度額です。 | |||
| ※年度上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。 | |||
- 外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額は、同じ世帯で同じ保険者である場合の合計額で算出します。
- 70歳以上の人はまず外来(個人ごと)の限度額を適用した後、外来と入院を合わせた世帯ごとの限度額を適用します。
保険証の使用制限
国民健康保険で治療を受けるときは、必ず事前に届出をしてください。
交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によって、ケガや病気をしたときでも、届出をすれば国民健康保険で治療が受けられます。ただし、医療費は加害者が負担をするのが原則ですので、国民健康保険が一時的に建て替え、あとで加害者に請求します。
届出は忘れずお早めに
国民健康保険で治療を受ける場合は必ず事前に住民生活課に連絡し、速やかに「第三者行為による被害届」を提出する必要があります。
様式等第三者行為求償事務《外部リンク》<外部リンク>
~ご注意ください~ 次の場合は国民健康保険で治療は受けられません
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
- 業務上のケガの時(労災保険の対象になります)
- 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき
示談は慎重に
国民健康保険に届出る前に示談をするとき、その取り決めが優先して、加害者に請求できない場合があります。安易に示談には応じないようご注意ください。
お問い合わせ先
大衡村住民生活課(手続き・給付に関すること)
電話:022-341-8512
Fax:022-345-4853
大衡村税務課(国民健康保険税に関すること)
電話:022-341-8513
Fax:022-345-4853