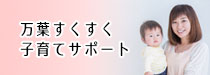本文
国民年金
国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方に加入が義務付けられています。
保険料を納め続けることで,年を取ったとき(老齢)やケガや病気で働けなくなったとき(障害),家族の働き手が亡くなったとき(遺族)などに基礎年金を受けることができます。
加入者の種類
- 第1号被保険者
自営業者・農業者とその家族,学生,無職の方など,第2号・第3号被保険者でない
20歳から60歳未満の人。 - 第2号被保険者
厚生年金や共済組合の被保険者(届出をしなくても国民年金に加入したことになります)。 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)。
ただし,事業主への届出が必要です。 - 任意加入者(希望で加入する人)
・日本国内に住所のある60歳以上70歳未満の人。
・海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人。
・厚生年金や共済組合の老齢年金の受給権者で20歳以上60歳未満の人。
国民年金の種類と年金額
| 年金の種類 | 内容 |
|---|---|
| 老齢基礎年金 |
|
| 障害基礎年金 |
|
| 遺族基礎年金 |
|
| 寡婦年金 |
※亡くなった夫が,老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。 |
| 死亡一時金 |
|
| 付加年金 |
|
保険料
- 保険料は,年齢・所得・性別に関係なく一律です。
令和5年度の保険料は月額16,520円です。 - 付加保険料
月額400円
第1号被保険者が毎月の保険料に月額400円の付加保険料を納めることにより,納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
保険料の納付方法
- 第1号被保険者
納付書により個別納付になります。口座振替やクレジットカード,スマートフォンアプリでも納付できます。
また、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができ、割引が適用されます。 - 第2号被保険者
保険料は,それぞれの年金制度から国民年金制度に支払われますので,個人で納める必要はありません。 - 第3号被保険者
保険料は,配偶者の加入する年金制度がまとめて負担するしくみになっていますので,個人で納める必要はありません。
詳しくは、こちらのホームページ<外部リンク>をご覧ください。
保険料の免除・納付猶予制度
- 保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出することで保険料の納付が免除になる場合があります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。 -
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請書を提出することで保険料の納付が猶予される場合があります。 - 学生納付(保険料)特例
学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
前年の所得が128万円以下であることが基準です。他の家族の所得の多寡は問いません。
学生納付特例の期間中は,保険料が追納されない場合は,老齢基礎年金の額の計算には反映されませんが,年金の受給資格期間には算入されます。
10年以内であれば保険料を追納することもできます。
詳しくは、こちらのホームページ<外部リンク>をご覧ください。
こんなときは届出を・・・
| 届け出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 厚生年金・共済組合をやめたとき (扶養している配偶者がいる場合は、あわせて届出が必要です) |
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) 年金手帳または基礎年金番号通知書 退職年月日の分かる書類 |
| 住所・氏名が変わったとき (マイナンバーが登録されている場合は原則届出不要です) |
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) 年金手帳または基礎年金番号通知書 |
| 任意加入するとき・やめるとき | 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) 年金手帳または基礎年金番号通知書 預金通帳および金融機関への届出印 |
| 海外へ転出したとき | 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) 年金手帳または基礎年金番号通知書 |
| 海外から転入したとき | 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) 年金手帳または基礎年金番号通知書 |